現地コラム
COLUMN

イリオモテヤマネコについて!生態や特徴、出会い方など現地スタッフが徹底解説!
みなさんこんにちは!
西表島最大級のアクティビティショップ
「西表島 ADVENTURE PiPi」です!
西表島といえば、みなさんイリオモテヤマネコを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
イリオモテヤマネコは、沖縄県にある西表島にしか生息しない絶滅危惧種の生き物です。
今回はそんな西表島のシンボルとして愛されているイリオモテヤマネコについて解説していきます!
目次
イリオモテヤマネコとは

イリオモテヤマネコはネコ科ベンガルヤマネコ属に分類されるベンガルヤマネコの亜種です。
そのため、見た目はヒョウ柄のベンガルネコに少し似ており、都会で見かける野良猫とは若干見た目が異なります。

約24万~2万年前の期間にイリオモテヤマネコの祖先が大陸から琉球諸島へ渡ってきたとされ、西表島に定住したものが現在の彼らです。
1965年に西表島の南西部にある船浮集落で発見されました。

しかし、このイリオモテヤマネコたちは年々数を減らしており、現在は絶滅危惧種としての指定を受けてしまっているのです。
その稀少さから特別天然記念物、国内希少野生動植物種に指定されており、現在では西表島の固有種として親しまれています。

島へ赴けばイリオモテヤマネコのグッズ販売や猫飛び出し注意の看板があるなど、島民から広く愛されている様子を目にできるでしょう。
現地の方言では「ヤママヤー」や「ヤマピカリャー」、「メーピスカリャー」などという呼称で親しまれています。
和名
イリオモテヤマネコ
英名
Iriomote cat
方言名
ヤママヤー、ヤマピカリャー、メーピスカリャー
生息域
沖縄県西表島
頭胴長
約50~60cm
体重
3~5kg
イリオモテヤマネコの特徴

ヤマネコと呼ばれていますが、イリオモテヤマネコの体長は50cm〜60cm、体重は3kg〜5kgと一般的な飼い猫とほぼ変わりません。
上記でもご紹介した通り見た目はヒョウ柄で、マンチカンのように胴長短足なのが特徴的です。
小さくて丸い耳で、額には縦方向に縞模様があり、目の周りは白く隈取りされたようになっているため目付きが悪く見えます。
イリオモテヤマネコの生態

イリオモテヤマネコが生息する西表島は沖縄県の離島で、沖縄本島よりもさらに400km以上南西にある八重山諸島の中の一つです。
遥か南方の立地であることから本土とは異なる亜熱帯気候に属していて、年間を通してその気温は非常に温暖です。

そんな気候が自然環境に好影響を及ぼし、島の9割以上がジャングルなのが西表島最大の特徴です。
ユネスコによって世界自然遺産の地として選ばれているほどで、海に囲まれているため外来種が環境を乱すリスクも低いです。
この安定した気候は少なからずイリオモテヤマネコの生息に影響しているでしょう。

そんなイリオモテヤマネコたちは夜行性で、日中の時間は基本的にジャングルの木陰や岩穴などで寝ています。
ただしそのような場所に常にいるというわけでもなく、島内の山麓から海岸にかけての低地部分の広範囲で目撃されます。
西表島の低地には河川や沢があり水も豊かのため、飲み水としても利用しているのでしょう。

雑食性であり、昆虫類、爬虫類、哺乳類などとにかく多種多様な生物を餌としています。
元来、西表島のような小さな離島にはネズミなどの小型の哺乳類が少数しか生息せず、それを餌とする生物が住むには適していません。
安定して捕獲できる餌が少ない環境への順応として類まれな雑食性を身に付けたのだろうと言われています。

また、猫を飼われている方だとご存知かもしれませんが、多くの猫は水を嫌うことで有名です。
しかし一方、イリオモテヤマネコは水に苦手意識がなく、寧ろ泳ぎが大得意な生き物となっています。

飢えをしのぐために川に飛び込んだり潜水したりして魚を捕まえます。
限られた環境の中でたくましく生き残ったこのサバイバーこそが、イリオモテヤマネコというわけです。
イリオモテヤマネコは何匹くらいいる?

イリオモテヤマネコの生息数は年々減少しているといわれており、現在では約100匹しか残っていないと推定されています。
今後絶滅してしまう可能性がとても高い動物だということが数からもわかりますね。
イリオモテヤマネコは絶滅危惧種?

そんなたくましさを誇るイリオモテヤマネコですが、上記で少し触れたように絶滅危惧種としての指定を受けてしまっています。
「国内希少野生動植物種」とは日本で生息する種の中で絶滅の恐れがあるものに対し、種の保存を目的として環境省が指定を出すものです。
その国内希少野生動植物種に、1994年にイリオモテヤマネコも指定されました。
イリオモテヤマネコが
減った原因

これほどたくましい生態を誇るイリオモテヤマネコが、なぜここまで減少してしまったのでしょうか。
その原因として挙げられるの4つの理由をご紹介していきます。
①開発に伴い生息地の減少

西表島の自然は世界的に見ても貴重なもので、島の90%以上が未開拓なままであるほど自然環境が保護されている土地です。
その一方、沖縄県の多くの島がそうであるように、観光業は西表島に住む方々にとって重要な産業となっています。
そのため西表島の観光地化は少しずつ進められており、宿泊施設や商業施設の建造を目的とした開発が進められているのも事実です。

他の土地に比べれば雄大なジャングルが残されている西表島も、道路改修や大規模な農地拡大などにより自然を少しずつ失ってきました。
結果としてイリオモテヤマネコが好む環境の舗装が進み、生息地として適さない環境へと少しずつ変化していってしまっています。
②交通事故

現在イリオモテヤマネコの生存数減少の原因として最も深刻に捉えられている問題は交通事故です。
西表島は年々観光客が増加しており、その多くがレンタカーを移動手段にします。

そんな観光客とイリオモテヤマネコとの事故が多発するのは夜間です。
西表島の夜は市街地以外にはあまり街灯がなく、曇天の日などは土地勘のない観光客にとっては特に視界が悪い環境となります。
イリオモテヤマネコの主な活動時間は夜ですので、不意に道路へ飛び出してきて接触といったケースでの事故が頻発しているのです。

1978年から2022年4月までの間でイリオモテヤマネコに関する交通事故は101件発生しています。
そしてそのうちの91件はイリオモテヤマネコの死亡が確認されています。
現在の生息数が100匹ほどであることから考えると事故件数が深刻であることがわかりますね。

また交通事故が多発する原因としてよく挙げられるのが、西表島に唯一通っている幹線道路がイリオモテヤマネコの生息地に近いという点です。
イリオモテヤマネコにとってはこの幹線道路も行動範囲内であり、そこを横切っているタイミングで事故に遭遇してしまったという件が多数。

さらにイリオモテヤマネコの発情期である冬季には雄や若いネコたちが活動的になるため、これも事故が多発する原因となっています。
環境省や沖縄県によりイリオモテヤマネコの飛び出しの注意を促す道路標識や動物用トンネル、ゼブラゾーンの設置などが行われています。
西表島に訪れてレンタカーを借りる際は、常に生き物の飛び出しを考えスピードを出さないようにしましょう。
③外来生物

離島の水に囲まれた環境は外来生物を寄せつけにくいですが、それでも外来種によるイリオモテヤマネコの死亡例もあります。
イリオモテヤマネコが外来生物に捕食されるのではなく、イリオモテヤマネコが外来生物を捕食して毒化することにより死亡することが多いようです。

そんな外来生物の一つとして挙げられるのがオオヒキガエル。
雑食であることから害虫駆除を目的として石垣島に導入された中南米原産の大型ガエルで、西表島にも分布しています。
ですが、現状から見ればこれは失策だったと言わざるを得ません。
オオヒキガエルは小動物などを無差別に捕食することから、西表島の生態系を崩してしまう恐れがあるのです。

そんな小動物の天敵であるオオヒキガエルもイリオモテヤマネコにとっては餌ですが、オオヒキガエルは耳腺から強い毒の液体を分泌します。
人間でも失明したり最悪の場合心臓麻痺を起こしてしまうほどの強毒で、イリオモテヤマネコが捕食すれば死亡してしまう恐れがあります。

石垣島に比べると西表島に生息するオオヒキガエルの数は少ないのですが、繁殖能力が非常に高いことから定着してしまうのも時間の問題です。
早急の手立てを考える必要がある、というのが現在の状況となっています。
④FIV

飼い猫などでも懸念されるFIV(ネコ免疫不全ウイルス感染症)、通称猫エイズによるイリオモテヤマネコの死亡も問題視されています。
FIVは主に感染している猫から喧嘩などをきっかけに唾液を媒介として伝染し、発症すると貧血や腫瘍の発生などの症状を経て数ヶ月で死に至ります。。

現在の動物医療でもこのFIVに対する有効な治療法はなく、野生の個体が罹ってしまえばひとたまりもありません。
実際にFIVでイリオモテヤマネコが死亡した例はありませんが、西表島での飼い猫から検出され死亡した例は報告があります。

野生のイリオモテヤマネコはワクチンを接種していないため、飼い猫との接触があればFIVが広まってしまう可能性は十分にあるのです。
今後の感染とその拡大を、十分に危惧しておかなければならない状況と言えます。
イリオモテヤマネコの生息地

上でもご紹介させていただきましたが、イリオモテヤマネコの生活圏は基本的には森の中です。
それに加えて海岸沿いの林や小道、湿地林、マングローブ林などの水辺も餌が豊富なことから主要な行動範囲に入ります。
ただし、人間が意図してその姿を見ることは難しいと言えるでしょう。

イリオモテヤマネコたちは基本的に夜行性であり、なおかつ注意深い性格のため森の中を歩いて探して回っても出会えることはほとんどありません。
仮に近くに潜んでいたとしても、耳と鼻がとても優れているため遭遇する前に逃げてしまうでしょう。

無闇に彼らの住居へと踏み込まず、出会うことが出来たらラッキー程度の考えに留めておくのが一番です。
もし遭遇できたとしても、絶滅危惧種の彼らの生活を脅かさないよう遠くから観察し、触ったり刺激することは決してやらないようにしましょう。
イリオモテヤマネコには
どうしたら会える?

会える確率も低い、住処に入らない方がいいならばどうしたら会えるの?
そんな疑問を抱く方もいるでしょう。
お次はイリオモテヤマネコに会える可能性がある方法をご紹介します!
①西表野生動物保護センターに行く

西表島には野生生物保護センターという場所があります。
施設ではイリオモテヤマネコなど西表島に生息する生き物の模型や詳細が展示されています。
虫や植物など幅広く展示されているため、西表島の自然について深く知ることができます!
住所
電話番号
0980-85-5581
営業時間
10時~17時(月曜定休日)
料金
無料
②夜の西表島を散策

先ほども記述して通り、イリオモテヤマネコは夜行性です。
そのため昼間の散策よりも夜間の散策の方が遭遇率が高くなります!
しかし夜の山に立ち入ることは大変危険なので、山沿いを散策するようにしましょう。
PiPiのキャラクターも
イリオモテヤマネコが
モチーフ!

ADVENTURE PiPiのマスコットキャラクターである「ピピくん」。
ピピくんも実は、イリオモテヤマネコがモチーフになっているんです!
イリオモテヤマネコと一緒にピピくんもぜひ可愛がってくださいね!
西表島のおすすめ
アクティビティ5選!

イリオモテヤマネコの生息する西表島の大自然はどんなものか、実際に体で感じて楽しむこともできます!
今回は西表島の自然を満喫できるアクティビティを5つご紹介します。
西表島のおすすめ
アクティビティ
①マングローブSUP/カヌーツアー

まずご紹介するのはマングローブSUP/カヌーツアーです。
西表島のアクティビティの中でも定番のツアー!

海上でゆったりと波を感じながら、自然に囲まれた川を進んでいくのはとても神秘的に感じます。
西表島の大自然は、眺めるだけでパワーを貰える素晴らしいスポットです。
西表島のおすすめ
アクティビティ
②バラス島シュノーケリング

世界遺産の島でのSUP/カヌーとバラス島でのシュノーケリングがセットになったプラン!
バラス島シュノーケリングでは運が良ければウミガメに出会うことも!
サンゴでできたバラス島周辺の海は透き通っていてとても綺麗です。
西表島のおすすめ
アクティビティ
③キャニオニング

キャニオニング(渓谷下り)とは、その名の通り渓谷を川に沿って下っていく遊びです!
キャニオニングは頭からつま先まで全身濡れるため雨が気にならず年間通して大人気のアクティビティ!
西表島の大自然を感じながらの冒険はワクワクすること間違いなしです。

崖からのジャンプはスリル満載なのでぜひ挑戦してみてください。
泳ぎが苦手な方もライフジャケットを着用するので安心です!
雨の日も川に飛び込んで爽快アクティビティを体験してみてはいかがでしょうか?
西表島のおすすめ
アクティビティ
④サンセットSUP/カヌー

西表島の自然界を全身で感じながら見るサンセットツアーは人気の高いツアーです。
壮大な夕陽を見ながら、SUPやカヌーで海をクルージングすれば、最高の1日の締めくくりができるに違いありません。
SUPもカヌーもガイドがしっかり指導するため、初心者の方でも安心して乗っていただけます。

現実世界を全て忘れて、自分と太陽と地球だけの時間が味わえます。
都会で見るのとはまた違った大自然の中で見るサンセットで大いに癒されてください!
西表島のおすすめ
アクティビティ
⑤星空&ジャングルナイトツアー

世界遺産に選ばれた西表島での星空&ジャングルナイトツアーはぜひ体験してほしいツアーの1つです。
本州では見ることのできない珍しい生き物や植物を見ることができます。
イリオモテヤマネコとは別の絶滅危惧種「ヤシガニ」を探してみてください!

晴れていたら満天の星空を見ることが出来るかも。
世界で2番目に「星空保護区」に認定された星空で、天然のプラネタリウム体験ができます!
日帰りではなく宿泊する方のみ楽しめる夜の西表島を堪能してください!
さいごに
西表島のシンボル、イリオモテヤマネコについてご紹介させていただきました。
愛らしく貴重なイリオモテヤマネコですが、野生の個体とは接触しないのが一番です。
旅行に訪れてイリオモテヤマネコと会いたいのであれば、古見集落の近くにある西表野生生物保護センターへと訪れましょう。
観光で島を訪れた際は、ぜひイリオモテヤマネコたちのことも気に掛けてみてくださいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
西表島PiPiでは一緒に働ける
仲間を募集中!
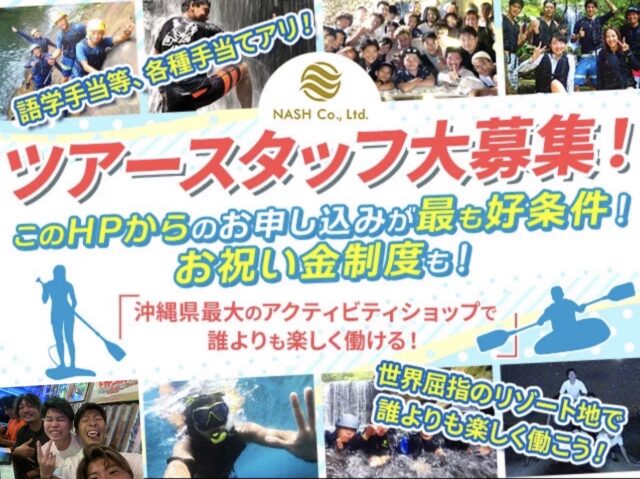
PiPiでは短期でも長期でも、年間を通じて一緒に働くスタッフを募集しています!
ツアーガイドをはじめ、事務職、マーケティング担当、営業スタッフ、バックオフィス人材まで、幅広い職種で積極採用中です。
未経験者歓迎!沖縄での移住や新しいチャレンジを考えている方も、ぜひご応募ください。
アクティビティ業界で働きたい方、沖縄の自然を舞台に活躍したい方、PiPiで新しいキャリアをスタートしませんか?

